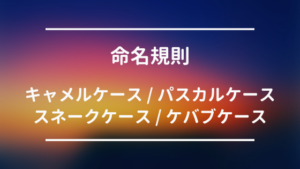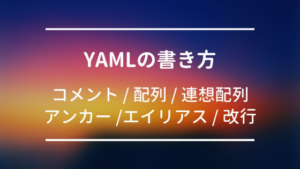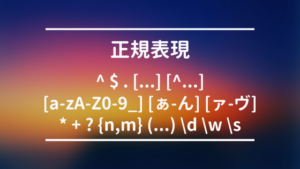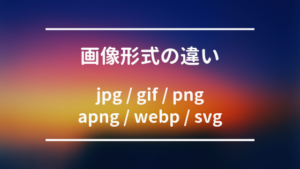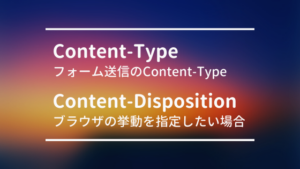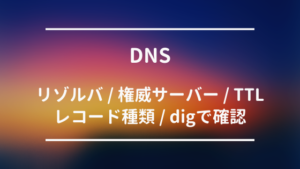CPUアーキテクチャの表記は、色々あり混乱します。
「x86」「x64」「x86_64」「amd64」「arm」「arm64」「AArch32」「AArch64」など、見かけます。
ここでは、CPUアーキテクチャの種類について簡単に取り上げます。
CPUアーキテクチャの種類
( x86, x64, arm )
x86x64armの違いについて確認していきます。
「x86_64」 「amd64」 という表記を見かけることもあります。混乱しますが「x64」と同じと考えて、まず問題ないです。
命令の仕方
x86 x64 は CISC(Complex Instruction Set Computer) と呼ばれる命令セットです。
「複雑な処理」を「少ない命令」で実行しようとする思想です。
arm は RISC(Reduced Instruction Set Computer) と呼ばれる命令セットです。
ビット数
ビット数が大きくなるにつれ、一度に処理できる量が増えます。処理スピードUP・利用可能なメモリ容量UPが見込めます。
x86, x64
x86 は 32bit です。x64 は 64bit です。
arm
arm については、ARMv7 では 32bit でした。ARMv8(2011年発表) では実行モードというのがあり、AArch32だと32bit 、AArch64だと64bit となるようです。(ややこしい…)
Linuxでは、ARMv7までのアーキテクチャの表記をarmとして、ARMv8アーキテクチャの表記をarm64としているようです。
用途
armは、スマホなどで主に利用されてきました。
パソコンやサーバーではx86/x64が市場を占めていましたが、2020年にApple社がPCにarmを採用した独自プロセッサを採用すると発表して話題になりましたね。
関連会社
( インテル, AMD, Arm )
x86 x64 は、インテル社、AMD社が開発しています。
長年インテルが市場を占めてましたが、AMDがRyzenシリーズを2017年に発売後、AMDの人気も高い印象です。
arm はArm社が開発しています。
2016年にソフトバンクグループがArm社を買収しました。その後、2020年にソフトバンクグループは、Arm社をNVIDIAに売却しました。
(売却契約は解消されました。)
確認方法
Linuxで確認したいとき、以下コマンドで確認できます。
$ uname -m
x86_64